第35話 " ザルツブルク 1 "
------音楽の町 ♪ Salzburg ♪------
♪ 『私のオーストリア旅行』で訪れた所では、唯一ザルツブルクだけが、行く前にはっきりとイメージが思い描ける場所でした。それは映画"サウンド・オブ・ミュージック"のせいです。サウンドトラックのLPレコードも買って、覚えた歌もありました。
そのとき、天才モーツアルトが生まれた町であることも、今ではすっかり有名になった、ザルツブルク音楽祭の行われる街である事も、私には大した意味は無かったのです。
ザルツブルク Salzburg のSalz〔ザルツ〕はドイツ語で塩、Burg〔ブルク〕は城あるいは砦で、名前の示すとおり、有史以前からこの辺りには岩塩が豊富に産出しました。岩塩の交易による豊かな富を背景に、中世からこの街には、ホーエンザルツブルク城を居城として、キリスト教の大司教が君臨しました。
スタンダールの恋愛論で、語られる「ザルツブルクの小枝」もここの塩抗の中でのことです。
東洋から見れば、オーストリアの片田舎、ザルツブルクは、昔は塩の町。そして今や、多くの観光客を集める音楽の国の超有名な音楽祭の街です。
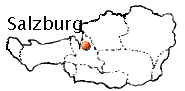
♪まずは、表敬訪問のためミラベル宮殿へ向かいます。我々を迎えるバロック様式の宮殿内には、天使の彫刻のついた、暖かな色の大理石の階段が、古典的な雰囲気をかもし出しています。現在は、宮殿内部でコンサートも開かれているので、ザルツブルクでの時間をゆっくりと過ごせる人は、美しい宮殿と音楽とを同時に楽しむことも可能です。
宮殿を出ればそこは、映画"サウンド・オブ・ミュージック"で「ドレミの歌」が歌われた、あのミラベル庭園です。外から見た宮殿の壁面から、1600年代に大司教の愛人のために造られた建物と、100年余りの後、継ぎ足された建物とが、建築様式の違いではっきりと見て取れます。
映画のシーンで見覚えのある部分を手繰り寄せ、パッチワークのようにつなぎ合わせて見るのですが、なにか違う。そこにはマリアも子供達もいないうえに、「ドレミの歌」が聞こえない、映画ではなく、明るい夏の太陽が降り注ぐ今があるだけです。
綺麗に手入れされた花壇には、緑の中に、ト音記号の形に花が植えられています。ウィーンのシェーンブルン宮殿でもそうでしたが、ひらぺったい空間です。その代わり、石の彫刻が随所にあり、周りは非常に高い生垣が張り巡らされています。庭園は思いのほか広く、砂利を踏んで歩きつかれ、所々にあるベンチに座れば、お尻がその曲線に包み込まれ、ヨーロッパの水準にちょっと足りない日本人の足は、宙に浮いてしまいます。でも我々は心も宙に浮いているからバランスとしては丁度いい加減。その気になれば、ちょっと散歩に出てホッと一息入れている住民の気分にだってなれます。
じっとして見ている映画の平面ではなく、我々は今、その庭園に立体的に参加しています。紛れも無く、この門はマリア達が手を広げて歌った所だと、誰も彼もが思い出し、確かめあい、歌ってみたり、踊ってみたり。所かまわずふざけて、目一杯楽しむ、オーストリア風心意気をその頃にはすっかりマスターできた我々でした。
♪.♪.♪.♪.♪.♪.
♪幾何学模様の庭園から上に目を移すと、真向かいには、小高い丘が見え、頂きにはホーエン・ザルツブルク城がそびえています。ミラベル庭園を出て、橋を渡りお城との間に広がる旧市街へ向かいます。下を流れるザルツァッハー川は、石灰分を多く含むことが想像できる、濁ったエメラルドグリーンで、昔から変ることなくとうとうと流れています。観光客の行きたがる所は、インスブルック同様、大体徒歩で移動可能な範囲に集中しています。
マリアテレジアの時代、売れっ子だった建築家フィッシャー・フォン・エアラッハ(名前の間に挟まった 〔フォン〕von は貴族の家系であることを示す)の設計による建築群に取り巻かれ、これまた見おぼえのある、馬の彫刻があしらわれた大きな噴水のある広場に到着。
♪映画を見て感動し、「マリアのようなお嫁さんが欲しい。」と言った人がいましたが、馬の噴水で、マリアと同じような格好で写真の撮りっこなどしていると、突然大きな鐘の音が響き始めました。一日に何回か決められた時間に打ちならされる〔グロッケンシュピール〕Glockenspiel(=chime)です。どうやらその時間に合わせて地元のボランティアの人が、我々をここに案内してくれたようで、説明を聞いていなかった私は本当にビックリしました。というのは、鐘の音は毎日いたるところで聞こえてくるのですが、耳をそばだてると、なんとここの鐘は、知っている曲を演奏しているではありませんか。塔の上でいくつかの鐘が揺れているのがよく見えます。
当然ですが、私のカメラではこの音は採れません。残念で残念で・・・。当時はホームビデオはおろか自動焦点カメラなんて、便利なものは無く、私のカメラは、焦点もシャッター速度も絞りも全て手動のでかくて重いアサヒペンタックス。旅行前にはかなり周到に用意したつもりでしたが、録音機器には気がつきませんでした。このとき以来海外旅行には必ず、録音できるものを携えていきます。例えば、ハイデルベルクの石畳を歩く私の靴の響きは、けっして買う事の出来ない私へのお土産です。
スペインのガウディもサグラダ・ファミリアに、グロッケンシュピールのもっと大掛かりな仕掛けを考えていたらしいと最近TVで知りましたが、石の西洋建築物に囲まれていると、その微妙な響きは、なんとも言えず心を和ませるものです。
♪.♪.♪.♪.♪.♪.
♪ザルツブルク音楽祭のメイン会場「祝祭劇場」は、もともと大司教の厩だったところ。三つの建物がつながった建て方をワザワザ滋賀県から、見学に行きそれを参考に造られた「びわ湖ホール」は家の窓から見えますが、リサイクルではないのに、何が建築家の胸を打ったのか私にはわかりません。
ザルツブルク音楽祭は、一流の人の手になるフェスティバルではありましたが、ヨーロッパは夏はコンサートはオフシーズン。まだまだ、一部の専門家のもの。ヨーロッパ以外から訪れる人もあまりなく、私たちの歩く町には、この町を愛して訪れる人々が散策していたに過ぎません。その後一人で、訪れたとき、おばさんが一人こつこつお掃除しているホールを裏口からのぞきましたが、祭の後の閑散とした空気があっただけ。残念ながら、練習中の楽団すらいませんでした。その後、この町は、この音楽祭が有名になるのに歩調をあわせて、その頃の優しさを脱ぎ捨て、洗練の度を高めていったように思われます。
【補 足】 ザルツブルクについてもう少し
【お詫び】
ただいま、スキャナーとの接続不能で画像作成が出来ません。しばらくお待ちください。
バックナンバーは書架にそろっています。どうぞご覧下さい。
[戻る]02.05.05 07:08:43